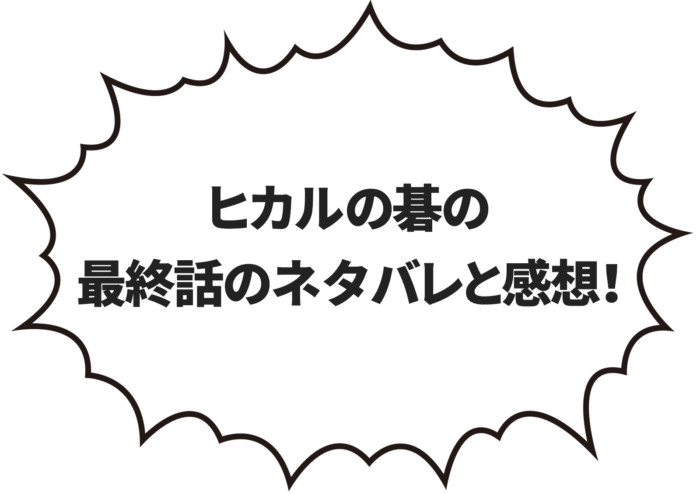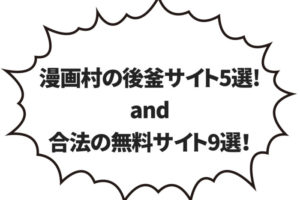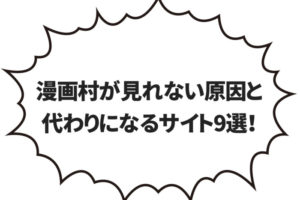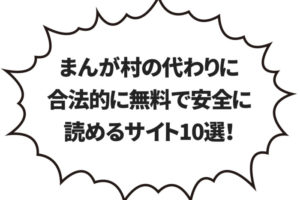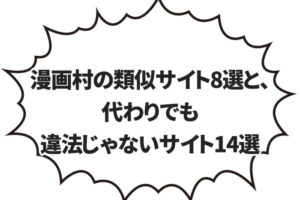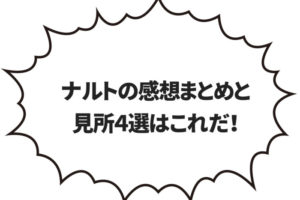「ヒカルの碁」は原作者のほったゆみさんと作画の小畑健さんがコンビを組んで、週刊少年ジャンプ1999年2・3合併号から連載を始めた漫画です。
テレビアニメや小説、ゲームなどのメディアミックス化もなされ、2000年には第45回小学館漫画賞を、2003年には第7回手塚治虫文化賞新生賞を受賞しています。
きっと、この漫画がきっかけになって囲碁を始めたかたもいらっしゃると思います!
今回はそんな「ヒカルの碁最終話」のあらすじ・ネタバレ・感想をお伝えしていきたいと思います。
目次
ヒカルの碁の最終話のネタバレ1 高永夏との勝負の行方
18歳以下の日本、韓国、中国のプロ棋士が参加する北斗杯で日本代表に選ばれたヒカルは、大将として韓国戦にのぞみ、韓国代表の高永夏と対戦します。
結果はヒカルの半目負け。
試合後、自分の力不足だと笑って話すヒカルに対し、高永夏は、笑ってごまかしてもムダだ、力の差を思い知っただろう、と辛辣な言葉を返します。
確かにヒカルは負けましたが、半目負けという、僅差の勝負です。解説会でも、大将戦にふさわしい一局だったと評されます。
また、高永夏自身も勝負をするなかでヒヤリとする場面があり、最後まで行方のわからない試合だったのです。
少年漫画で主人公が勝負に負けて終わるというストーリーは珍しいのかもしれません。
しかし、現実は理想通りにいくとは限りませんし、むしろ上手くいかないことのほうが多いかもしれません。
ヒカルが勝って、日本代表が優勝するというエンディングではありませんでしたが、意義のある勝負だったと思います。
主人公だって負けることはあるのです。
ヒカルの碁の最終話のネタバレ2 碁を打つ意味
勝負に負けたヒカルに、韓国代表の洪秀英が、なぜ碁を打つのかと問います。歯を食いしばりながら、ヒカルはそれに答えます。
ヒカルが碁を打つ意味、それは「遠い過去と遠い未来をつなげるため」でした。この言葉を発したあとに、負けたことが悔しい、とヒカルは涙を流します。
このヒカルの答えは、これからのヒカルの人生の意義、そして、いなくなった佐為への思いも含まれていると思いました。
佐為はヒカルの生きている時代の人間ではありません。しかし、ヒカルと出会ったことで佐為のいた過去と、ヒカルのいる現代がつながりました。
そして、きっとヒカル自身も佐為とふたりで培ってきたものを、未来に繋げていくのでしょう…。
そんな想いを感じるステキなセリフでした。
ヒカルの碁の最終話のネタバレ3 他の棋士たち
北斗杯には各国代表の関係者だけではなく、彼らの試合を観るためにギャラリーが集まっており、そのなかには一般の囲碁のファンだけではなく、伊角や和谷といった棋士たちの姿もありました。
ヒカルの友人、またはライバルでもある彼らは、北斗杯の表彰式が始まる前に席を立ちます。
表彰式には興味がないと、先ほど見た日韓戦の検討をすることにするのです。
そして、今年だけだったはずの北斗杯ですが、予想以上に注目されたため、来年も開催される可能性がでてきました。
最終話、日本代表は北斗杯で優勝することはありませんでしたが、決して負けて終わり、ではなかったのです。
今回日本代表に選ばれなかった棋士たちもまた、触発され、自分の未来のために前へ進んでいることがわかるシーンです。
それぞれの神の一手を極めるための貪欲な姿勢に、内に秘めた闘志が見えたような気がします。
ヒカルの碁の最終話のネタバレ4 終わらない未来
韓国戦でアキラは唯一日本代表として一勝をあげます。しかし、アキラもそれに満足はせず、前に進むため、未来を見据えていました。
勝負に負けて席を立てないままでいるヒカルに「終わりなどない」と声をかけます。
そして、過去と未来をつなげる棋士達が前に向かっていく姿を見せて物語は終わります。
この最終回で気になるのは、これからヒカルたちに何が待ち受けているのか、ということです。
けっきょくヒカルは佐為と再会できていませんし、高永夏にも負けたままで物語は終わってしまいます。
しかし、だからこそ、たくさんの未来の可能性を私たちに見せてくれてもいます。読者は自分の頭のなかで、未来の彼らの姿を想像することができるのです。
ヒカルはもう佐為と会えないままかもしれませんし、神の一手に近づけないかもしれません。
けれども遠い未来、誰かが神の一手を打つかもしれません。
1人の棋士の人生が終わっても、棋士という存在がある限り、未来はつながっていくのです。
ヒカルの碁の最終話の感想
ヒカルの碁の素晴らしいところは、囲碁をまったく知らない人でも楽しく読めるというところです。
そして、ヒカルという1人の少年の成長を見守ることができる作品でもあります。ときにはヒカルの感情がこちらに伝わり、涙が出てくるシーンもありました。
王道の少年漫画ですが、ありふれた物語ではありません。子どもに囲碁ブームを起こしたとも言われている作品ですが、それも納得です。